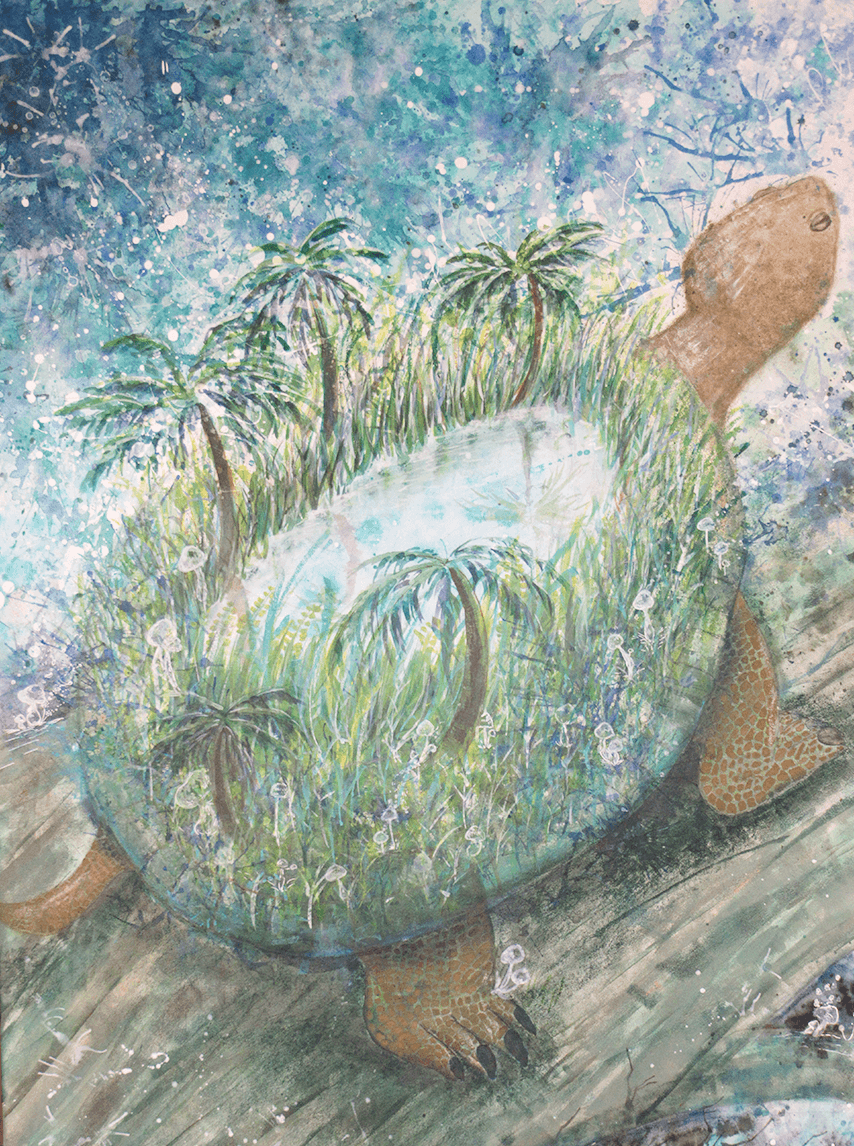12月21日(金)、平成30年度2学期 終業式を行いました。
諸先生方から、2学期の取り組みを振り返るとともに、冬休み中の過ごし方についても話しがありました。皆さん、この冬休みをケガや事故の無いように過ごし、始業式で元気な姿を見せてください。式の後には、表彰を行いました。


表彰
スポーツ部門
- 平成30年度校内マラソン大会
- 中学の部
第1位 2年B組
第2位 1年A組- 高校の部
第1位 2年5組
第2位 1年1組
第3位 2年4組
- 平成30年度中学校新人体育大会 埼玉県中学校体育連盟 主催
- 第3位 大妻嵐山中学校
文化部門
- プログラミング・プレコンテスト 埼玉工業大学 主催
- 優秀賞
1年(木藤・栗原・横山)
- 東京理科大学坊ちゃん科学賞 東京理科大学、東京理科大学理窓会 共催
- 優良入賞
大妻嵐山高等学校 ウミホタル班
- 第47回私学文化祭作品展研究発表部門 埼玉県私立中学高等学校協会 主催
- 佳作
・「マイハギの旋回運動と音の関係性」
・「小魚の視運動」
・「ウミホタルの発光条件」
・「ハエトリソウの研究」
- 埼玉県児童生徒理科研究会菅谷班研究発表会 埼玉県児童生徒理科研究会 主催
- 優秀賞
「ハエトリソウの研究について」(正木・中島・梶田・木藤・長野)
- 第61回埼玉県高校美術展 埼玉県高等学校文化連盟美術・工芸専門部会 主催
- 奨励賞2年(河合)
- 平成30年度薬物乱用防止啓発ポスターコンクール
- 優秀賞
3年(須田)
埼玉県薬剤師会長賞
2年(内田)
- 平成30年度全国中学生人権作文コンテスト埼玉県大会 東松山人権擁護委員会競技会地区予選 さいたま地方法務局東松山支局・東松山人権擁護委員協議会 共催
- 優秀賞
2年(仲)
1年(佐藤・橋本)
- 第57回伊勢神宮奉納書道展 伊勢神宮
- 伊勢賞
3年(橋本)
神宮崇敬会賞
3年(中里)
- 第46回全国学生比叡山競書大会 比叡山書道連盟 主催
- 比叡山書道連盟賞
3年(市原)
朝日新聞社賞
3年(福田)
- 第42回埼玉県アンサンブルコンテスト高等学校地区大会 埼玉県吹奏楽連盟 主催 クラリネット三重奏
- 銀賞
2年(木村・吉田)1年(小原)
朝日新聞社賞
3年(福田)
進路指導主任の話
今日は、目標を持って生きるということについてお話します。
12月11日スウェーデンのストックホルムでノーベル賞の授賞式があり、
京都大学の本庶佑特別教授が、癌免疫療法の研究によりノーベル医学・生理学賞を受賞しました。
免疫とは病原体や異常細胞を排除する人体の働きです。癌免疫療法は人体が持っている免疫力を働かせて癌細胞を死滅させようとする治療法です。しかし、癌細胞は免疫を逃れる仕組みを持っているため、免疫療法は長年失敗続きでした。本庶教授は、この免疫を逃れる仕組を働かないようにする薬、すなわち免疫チェックポイント阻害薬を開発し、免疫が癌細胞に働くようにすることに成功しました。
癌は日本人の死因のトップで、2017年に約37万人の方が癌で亡くなり、死因全体の28%になっています。世界では年間880万人の人が癌で亡くなっていて、癌は人類が戦っている病気の中で最難関のものです。爪と髪の毛以外の人体組織は癌になる可能性があり、一度できた癌は体中のあちこちに転移しして人を死に追いやります。高齢化の進行により、日本人の2人に一人は癌にかかり3人に一人は癌で亡くなる時代となりつつあります。若い方の癌も多く、10代後半~20代の死因の約1割を占めています。社会の第一線で活躍している方が癌で突然亡くなり、ニュースになることがしばしばあります。癌は多くの人の人生を奪っています。
従来の癌治療は、手術、放射線治療、抗癌剤の3つ方法を組み合わせていますが、治療の効果は十分ではありませんし、治療困難な癌も多くあります。一方、癌免疫療法の試みは失敗の連続で、効果がないという評価が定着していました。
本庶教授は医学界で見放されていた癌免疫療法に挑戦してただ一人の道を歩み、1999年に免疫チェックポイント阻害薬による癌治療の論文を発表しましたが、だれにも信じて貰えませんでした。その後も周囲の無理解や偏見と闘いながら研究と開発を続け、2012年に医学界の誰もが認める癌治療の成果を上げて一躍脚光を浴びることとなりました。2014年には癌治療薬「オプジーボ」が発売され、末期癌治療に成功するなど、癌治療に革命をもたらしました。但し、「オプジーボ」による癌治療はスタートしたばかりで、まだ特定の癌にのみ用いられ、薬が効くのは投与された患者さんの2割程度です。しかし理論上は殆どの癌に効果がある可能性があるので、今後の発展が期待されています。
本庶教授は高校生の時、外交官、弁護士、医師のどれを目指すかで迷ったそうです。「多くの人を助けたい、医学で新しい発見をすれば何万人、何千万人もの役に立てる」と考えて京都大学医学部に進学し、研究者の道を歩みます。研究の原動力は好奇心と未知の領域へのチャレンジ精神だったそうです。「何のために研究をするのかといえば、知りたいことがあるから」また、「誰も見向きもしないテーマを見つけてそれを育てること、橋の無い山奥に初めて丸木橋を架けることが私にとっての喜びであり、丸木橋を鉄筋コンクリートの橋にすることではない」と言っています。小中学生に対しては「何か知りたい、不思議だなと思う心を大切にすること。教科書に書いてあることを信じない。常に疑いを持ち、自分の目で見て、納得するまで諦めない。そういう小中学生に研究の道を志してほしい」と言っています。
今後の研究の展望については「オプジーボが効く人と効かない人を早く見分けられるようにしたい」といって、どんな人にも、どんな癌にも効果的な癌免疫治療の研究に取り組んでいます。今後10~20年の間に大きな前進があり、癌免疫療法が癌治療の主役になることが期待されています。
本庶教授はノーベル賞受賞講演で「人類は21世紀のうちに癌を克服する。人は癌で死ななくなる。」と言っています。数十年後、あなたたちの多くが癌免疫療法に救われる可能性があります。あなたたちは癌で死なない最初の世代になるかもしれません。癌免疫療法は数百万人の命を救う可能性を秘めています。
本庶教授の偉業はすべての人の生き方の指針になります。
それは常に目標をもって生きることです。私はこれをやりたいというものを持っていることです。
教授の目標は、大きな目標から具体的な目標へ、一生の目標から短期的目標へと整然としています。
人の役に立ちたい→医学で人を救う→免疫学で人を救う→癌免疫療法の確立→薬品の開発
中学生・高校生も現時点での将来の目標をもっているべきです。その目標は変わるかもしれませんが、そもそも目標を持っていなければ変えることすらできません。
進路指導をしていて痛感することは、自分から目標を探すことの大切さです。
そのためには学ぶ事と自ら考えることが必要です。世の中を知らなければ目標は見つかりません。また、自分が何をすべきか考える力が無ければ目標は見つかりません。
読書などを通じて知識を広く求め、自分から学び考える必要があります。
今年の3年生の大妻女子大学進学者は進学内定後、3学年の先生方よりSDGSの研究の課題レポートが課せられました。SDGS とは国連が設定した、持続可能な開発目標のことで、生徒は貧困、飢餓、格差解消、女性の人権、エネルギー問題など、自分の進学する学部学科に関係する社会問題について学び、レポートを作り、皆の前で発表しました。
学ぶこと、考えること、レポートを作ること、発表することの4つの取り組みを通じて、自分の将来の目標を深めてもらいたいという意図があります。
学び成長することによって目標が変わることもあります。かつて出会った生徒の例をお話します。
大学文学部在学中に理学療法士になることを決め、障害を抱えた人のリハビリテーションをサポートしている人。せっかく就いた気象予報士の職を捨てて海外青年協力隊としてアフリカに行き、理科教育の普及に尽力している人。彼女らは自分を生かして活動する場を社会貢献に求めました。
社会貢献とは自分を犠牲にして他人のために尽くすということではありません。
社会貢献とは自分が社会の中で有意義な活動の場を得るということであり、自己実現そのものです。
幸福とは富、社会的地位、名誉などを得ることではなく、自分を生かす活動の場を得ることです。
本庶教授は講演の最後に「癌で死なないことは人にとって幸福か?」と問いかけています。医師にとって当たり前な「病から人を救う」ということの意味を問いかけています。
この問は、生きることの意味を問いかけたもので、すべての人に投げかけられたものです。
健康に長生きするのは幸運ですが、それだけでは幸福とは言えません。自分が生きていることに意義を見出せなければ幸福ではありません。ただ生きるのではなく、目的を持って生きること。自分を生かす活動の場を持つこと。それがわれわれが目指すべき生き方です。この冬休み、そして来年もあなたたちの目標に向かって大いに学んで行ってください。