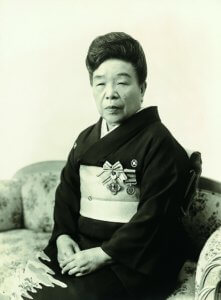大妻コタカ先生の言葉30
1 恥を知れ
大正 6 年、「私立大妻技芸学校」設立にあたり、大妻家の家訓「恥を知れ」を校訓として制定。他人に対して言うのではなく、自分の心に問いかけるもので、自分を高め、自分の「良心」に対して「恥ずるような行いをしてはならない」と自分を戒め律する言葉。
2 らしくあれ
人間らしい人間、女性らしい女性、そしてあくまでも自分らしい個性を持った自分を養い育てていきたいものです。身を変じてその都度それらしくなるにしても、それは外に現れた化身であって、根本にはいつも変わりなく輝いているところの個性がなければなりません。まず立派な個性を作りつつ、それが立場に応じ時に従って「らしく」現れるようにしたいものです。
3 日々の誓い
コタカ先生は毎朝の日課として、次の言葉を心に誓っていました。
「今日一日腹を立てぬこと」
「今日一日不平を言わぬこと」
「今日一日うそを言わぬこと」
「今日一日人の悪口を言わぬこと」
「今日一日何事にも感謝すること」
4 感謝の生活
私はいつでも和やかに平らな気持ちで、できるだけ善意に解釈して、すべてに感謝の気持ちを持ちたいと思っております。感謝とか有難いとかいうことは決して強制的ではなくて、ごくありのままの感情から流れ出る気持ちだと思います。私どもは毎日の生活にいかに多くの恵みを受けているかと考えますと、どんな小さなものにも、つまらないことにも精一杯の愛情をもって生きようと思います。
5 心美人に
私個人のことを申しますと、生まれつき顔や姿はどうにもなりませんが、心だけは自分の心がけ次第でどんなにでも変えることができると思いました。それで、何とかして私は日本一の心美人になろうと念じました。いつも明るい、正しい、そしてどんな人からも親しまれる円満な人格を創り上げるために、努力し勉強し続けたいと祈りました。
6 理想は高遠に実行は足元から
「理想はどんなにでも大きく、高く、立派に、貴く描くがよい。しかし一足飛びにそれを現実化させようとすると危険である。実行は足元から一歩一歩と進んで行かなければならぬ」と校主・大妻良馬は常に高唱しておりました。
7 有言実行
私の今日を築いてくれましたのは、言ったことは必ず実行するという主義で、責任を持ち人の嫌がる仕事はまず自分でやり、その中から人間学を学び取るということをモットーとしておりました。そして日常のほんのちょっとした小さなことでさえもその一つ一つに立派な意義があることを悟りました。
8 失敗すればそれが一つの体験になります
若い時代には、大いに外に向かって自分を進ませて見る必要があると思います。失敗すればそれが一つの体験になります。一番大切なことは、それにくじけないだけの勇気が欲しいということです。 私は随分あらゆることに頑張ってきたつもりですが、今になって振り返ってみますと、もっと自分を試みるべきだったと悔やむことがたくさんあります。ですから可愛い子どもたち(教え子たち)に、私に代わりうんと張り切って、若い時代を充実してもらいたいと望んでいます。
9 学ぶとは
学ぶということは、自分の心に問い、自分の心に応えて、自分のものとして、その心の中から出た力によって進んでゆくことをいうのです。日々、己の心を省みる、それは自分の一生を最も幸福に良くする根本になるということを考えていただきたいと存じます。
10 真の学問
私どもはいつも世の常道のみ歩行することを許されない場合が多いのですから、場に応じた処置を取り得る準備を常に備え、どんな事柄に突き当たっても、悠々自適に善処することのできる応用自在の力を要します。私どもの処世に必要な教養は、また社会で求められているものですので、学問に向かっては、ただ一点の高下を争う点取り虫式の勉強を排し、学校に学んだ人として人格的にもっと磨かれ、学校で学び得た知識がすべての生活に活用し得る人になっていただきたいと思っております。
11 賢くあれ
賢い人というのは、同じ過ちをくり返さない人をいうのであって、過ちをおかさなかった人ではありません。人間である以上、注意していてもいつか知らない間に過ったことをし、思うべからざることを考えるようなことがしばしばありますが、これはいけないと感じたとき、すぐに反省して、再びしてはいけないこと、考えてはならないことを繰り返さない人が本当の賢い人であるというのです。
12 ほめあいたい
ある時、吉岡弥生先生(※)が「大妻さんは美人とはいえないが、笑い顔は実にいい」と褒めてくれました。褒めていただき私の気分は満更でもなく、その時の吉岡先生もまことにご気分がよさそうでした。褒められると人情の常で、始終笑顔で暮らしたいと心がけます。ほんのさりげない言葉一つでその日が明るくも暗くもなるのなら、ほめあうことは生きた宝石といえましょう。(※東京女子医科大学創立者)
13 いつでも何処からでも何からでも学べ
学校を一歩出ますと定まった先生による教育はありません。これからは、実生活の周辺から、心に触れ目に映るものすべてを心身両面の糧として、生活の智恵を汲みとることに心がけましょう。
14 静かな実行家に
社会には口先ばかりの物知りが多くて困ります。およそ口達者な人ほど何もしないのであります。自分が何もしないから、せめて口だけとなり喧しく(やかましく)言わざる得なくなります。誠に見苦しいものです。どうか皆様は、口の人よりも手の人になってください。喧し屋にならないで、静かな実行家になってください。
15 「口まめ」を戒める
一度口に出したこと、言い過ぎたことは取り戻すわけにはいきません。まして人の悪口を言うことは慎まなくてはなりません。 人の悪口を言う人は、また自分の言ったことを他へ漏らす口軽な人ですから、決して先方の悪口に相づちを打ったり賛成してはならないのです。こんなときは努めて沈黙しているか、あるいは無邪気な方向へ話題を転ずるかに限るのです。
16 心ゆくばかり働きましょう
私共がこの世の中を愉快に暮らしていくには、いつも何かせずにはいられないという、生き生きした心持ちを続けて行くことが必要です。する仕事がなくなったら積極的に仕事を作って働いてください。その心がいつも清々しく、身体まで元気になり少々の病気は逃げてゆきます。心ゆくばかり働いた時ほど楽しい事はございません。
17 隣を愛する
自らを過信するときに、人間はとかく謙譲の美徳を失い、従順さを忘れるものです。人の生活には必ず隣があります。私どもを幸福にするときにも、不幸に陥れるときにも、隣の力がつねに大きく働くのでございます。皆様が社会においてよく融合しうるよう、そして隣を愛し、隣を益し、隣とともに栄えるように努められるよう念じております。
18 長所と短所
長所を見出しこれを伸ばすことの困難と等しく、その短所を矯(た)めることは至難なことです。私共は深く自分を省み、何事にもあれ誠意ある人の忠言にはまず心から耳を傾け、たとえどんな言葉にもせよ、怒らず恨まず、誠心誠意を以てこれを考えることです。
19 美しい行儀は美術中の美術、しかも活きた芸術
「美しい行儀」詳しくは、礼儀にかなった言葉、作法の整った動作は、絵画、彫刻と同様に美しくて、しかも活きています。絵画にまさり彫刻にまさる「美しき行儀」は、また容貌にまさり服装にまさるものです。
20 根のごとく
内に隠された意志の強さは表面には見えませんが、この根があればこそ人の心を和らげる花の美しさも生まれるのです。どんな困難も根のような堅い信念ではねのけていく力強さをもち、皆に好かれるようにいたしましょう。
21 塩のごとく
人間にはしなければならないことや、してはならないことがたくさんあります。社会という大きなクラスの中にあって、皆と手をくんで、自分のするべきことをきちんきちんと果たして、社会でも、学校でも、家庭でも、塩のようにより良いなくてはならない存在になりましょう。
22 人の和
家庭に職場に、広い狭いにかかわりなく「和」を土台として人と人との関係を結ぶことこそ大切で、清く正しい愛情でほのぼのした美しい人の和を創ることは平和な社会や家庭を構築する幸福への鍵であると思います。
23 柳は教える
柳の枝が雪を耐え忍ぶ力は、雪の重みをその時その時に素直に受け流して、最後に本当に自分を完全に生かしていこうという、いわば「敗けて勝つ」力です。敗けている人を弱いと思ってはいけません。心の力が強ければこそ、自分を抑えて敗けていることが出来るのであって、こんな人こそ真に強い人なのです。
24 みんな美しく
美しいものは接する人の心を、また自分の気持ちも明るくしてくれます。いつまでも若く美しく、せめて身だしなみだけでも、まず整えていきたいと思います。それに豊かな心を盛り、生き生きとした日常生活の間に、いろいろの苦しみを乗り切れる心の準備をしたいものです。若い人もお年寄りも、みんな美しく、明るく、快い生活へ、まず一歩を踏み出してまいりましょう。
25 強く正しくにこやかに
強い意思と、正しい判断と、にこやかな情緒が人として最も大切です。愛想のよいにこにこ顔の周囲にはいつも明るい春のような世界が現れてきます。家族の幸福も店の繁昌も、近所や社会の円満な交際もみなこのにこにこ顔から生まれてくるのです。
26 進んで人のために
自分のことは自分でする習慣を養うこと、進んで人のためになることをして御恩がえしをする心掛けが必要です。また互いに礼儀を重んじ相謙譲して円満に出来るだけ人の厄介にならないようにすることも大切なことです。
27 仕事に追われずに
学校はこれからの生活の土台作りで、卒業した後の本当の向上発展への努力と研鑽はこれからの勉強如何に関わります。どうか仕事に追われることなく追ってゆく前向きの姿勢をもって日常を過ごしてゆくよう心掛けていただきたいと思います。
28 時間の厳守
学生の遅刻欠席はこの上ない恥と同時に、精神上その他あらゆる学習上のどれだけ損失になるか、この悪習慣が継続したならば、その当人の一生涯にどれだけの不幸を招くかはかり知れません。時間を厳重に守らなければなりません。
29 七ころび八起き双六上がりけり
何事も一つのことを成しとげるには、いろいろなさわりがあります。このさわりがあるために、努力、勤勉、奮闘といった元気がわいてくるのです。七ころび八起きしているうちに、ままならぬ双六もついには「上がる」時がくるのです。
30 社会のために大きく貢献させていただきます
私が教職員と共に教育方針を貫いて参れましたのも、皆様方のお力添えによるものでございます。私の一番嬉しいことは、創立者の私が60周年の式典をこうしてさせていただく、本当に有り難いことでございます。私思います。この分ならまだまだ学校を経営していける。423名の教職員は一致協力して教育に当たってくれています。今後も大磐石の上にあって、社会のために大きく貢献させていただくという覚悟を持っております。(創立六十周年式典式辞より 1968(昭和 43)年 於日本武道館)
※コタカ先生はこの1年3ヶ月後、明治、大正、昭和の激動の時代に女性教育者として力強く進んできたその歩みを止め、自らの波乱に富んだ人生に幕を閉じられたのです。